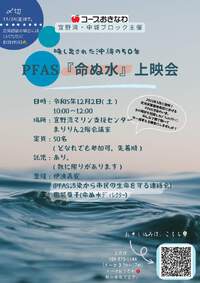6月25日(土)おきなわ環境塾 塾長の後藤道雄さんを講師に第3回目の学習会を行いました。
今回は、北中城村にあるおきなわ環境塾の学習棟『ぬちゆるやー』が会場です。

タイトルは「湧き水教育と水保全~現代社会における湧き水の意義~」

台風の影響もありましたが、自然の中に立てられた木造の建物の中は思った以上に静かで(周りの木々に建物が守られているかのようで)風の音、雨の音、が心地よく響きました。

後藤さんはまず、『湧き水fun倶楽部』は湧き水をどうしたいのか?
キツイこともいうかもしれないが、是非、活動をする上で考えてほしいことを話すつもりだというお話しから入りました。
湧き水fun倶楽部の活動は、湧き水の現状、湧き水をとりまく歴史や文化、自然環境を学び、その情報をできるだけ多くの人たちに伝えることを目的に行っていますが、自然科学分野の情報がかなり不足しており、湧き水のメカニズムや水源保護についてのお話しを是非後藤さんからお聞きしたかったというのが、今回の学習会のねらいでした。
耳の痛い言葉から入った学習会は、一気に緊張感が高まりました。
最初のテーマは「名水百選と教育」
ぬちゆるやーのある北中城村荻道とそのお隣にある大城地区には今も質のよい湧き水が点在しており、今から3年前に『荻道大城湧水群』として平成の名水百選に選ばれ、地域の方達によって湧き水が大事に守られています。
その名水百選に名乗りをあげ、尽力された仕掛け人ともいえる後藤さんは、環境教育を手段とした人間形成を目的に湧き水の活用、保全に積極的に取り組んでいらっしゃいます。

湧き水マップを渡して、その場所に置かれたスタンプを押すスタンプラリーは子どもたちに大人気なのだそうです。
湧き水を案内することで湧き水をより理解してもらおうという気持ちが私は大きかったことに気づかされたのですが、自分で探しに行く!見つける!!という行為そのものが、湧き水を知る上で重要なのかも知れないと感じました。
「教育」という言葉からは、未来に向かって伸びる子どもたちを育て教えるという大きな使命を感じますが、それだけではなく人が自ら学ぶ意志を引き出すことや環境を整えることもとても大事なことだと感じました。
「湧き水教育」という言葉の意味を更に深く考えていきたいです。

このマップには10箇所の湧き水が示されてあり、それぞれの湧き水の情景が伝わるように工夫をされているひとつひとつのスタンプもとてもステキです。
実際に荻道大城には10箇所以上の湧き水があるそうですが、昔から水争いのあったこの2つの地域が水で仲良くなれるようにと名水百選では、それぞれ5つづつ選らぶという気遣いがあったという裏話も披露されました。「水に流そう~」って。(笑)厳しい中にもちゃめっけたっぷりな後藤さんの笑顔に緊張はすっかりとけてしまいました。
続いて2番目のテーマである「湧き水のメカニズム」

金武町と荻道大城の航空写真や断面図などを比べての説明はとてもわかりやすく、沖縄の湧き水の特徴とも言える琉球石灰岩台層の大きさが水量であるということが納得できました。
そして地下水の保全をするためには、できるだけ水を地下に浸透させることが大事であること。
そのためには普段から緑、土、命を意識することが大切だということがわかりました。
アスファルトの舗装などで雨水が側溝を通して流れ出ることで起こる危険な都市型洪水を防止するためにもとても重要なことで、地下水のメカニズムを知ることは、自然を守ること、命を守ることにつながります。
「水は40日で一回転」
「すでる(沖縄の方言では『すでぃる』)と言葉もあるように命は常に生まれ変わるもの。水は天からのもらい水であり、天に返さなければいけないものである」
常に神聖な気持ちで水に向き合いたいと思いました。それには謙虚な姿勢が大事なのだと感じます。

「名水百選の森の創出」
この曼荼羅図には、荻道大城の遺産や町並み、文化、そして湧き水が描かれており、その中心には森があります。
「森へつづくまちづくり」
地域の方々は名水によってこのようなすばらしい実践をされていることにとても感動を覚えました。
講演の内容をすべて記すことはできませんが、最後に後藤さんは私たちにこう問いかけました。
「カー(湧き水)は人間のためにあるのですか?」
地震、津波、台風、湧水、温泉
これはすべて自然現象です。
敵視してはいけない。
人間もその自然の中の一部にすぎない。
自然に会わせて生き物と同様に自然と共に暮らすという気持ちが大事なのではないか。
湧き水を自然共生のシンボルとして残すという視点を是非持っていてほしい。
そして、水に命を吹き込むという活動も必要。
科学的な物の見方も重要だが、やはり文化的な見方も大事。
それには『感性』が必要。
後藤さんの哲学ともいえる内容の濃いお話しを租借し、受け止め活動に結びつけていきたいと思います。
お忙しい中、本当によいお話をありがとうございました。

受講生の質問に答えながら中柱の説明をする後藤さん。
今回は、北中城村にあるおきなわ環境塾の学習棟『ぬちゆるやー』が会場です。

タイトルは「湧き水教育と水保全~現代社会における湧き水の意義~」

台風の影響もありましたが、自然の中に立てられた木造の建物の中は思った以上に静かで(周りの木々に建物が守られているかのようで)風の音、雨の音、が心地よく響きました。

後藤さんはまず、『湧き水fun倶楽部』は湧き水をどうしたいのか?
キツイこともいうかもしれないが、是非、活動をする上で考えてほしいことを話すつもりだというお話しから入りました。
湧き水fun倶楽部の活動は、湧き水の現状、湧き水をとりまく歴史や文化、自然環境を学び、その情報をできるだけ多くの人たちに伝えることを目的に行っていますが、自然科学分野の情報がかなり不足しており、湧き水のメカニズムや水源保護についてのお話しを是非後藤さんからお聞きしたかったというのが、今回の学習会のねらいでした。
耳の痛い言葉から入った学習会は、一気に緊張感が高まりました。
最初のテーマは「名水百選と教育」
ぬちゆるやーのある北中城村荻道とそのお隣にある大城地区には今も質のよい湧き水が点在しており、今から3年前に『荻道大城湧水群』として平成の名水百選に選ばれ、地域の方達によって湧き水が大事に守られています。
その名水百選に名乗りをあげ、尽力された仕掛け人ともいえる後藤さんは、環境教育を手段とした人間形成を目的に湧き水の活用、保全に積極的に取り組んでいらっしゃいます。

湧き水マップを渡して、その場所に置かれたスタンプを押すスタンプラリーは子どもたちに大人気なのだそうです。
湧き水を案内することで湧き水をより理解してもらおうという気持ちが私は大きかったことに気づかされたのですが、自分で探しに行く!見つける!!という行為そのものが、湧き水を知る上で重要なのかも知れないと感じました。
「教育」という言葉からは、未来に向かって伸びる子どもたちを育て教えるという大きな使命を感じますが、それだけではなく人が自ら学ぶ意志を引き出すことや環境を整えることもとても大事なことだと感じました。
「湧き水教育」という言葉の意味を更に深く考えていきたいです。

このマップには10箇所の湧き水が示されてあり、それぞれの湧き水の情景が伝わるように工夫をされているひとつひとつのスタンプもとてもステキです。
実際に荻道大城には10箇所以上の湧き水があるそうですが、昔から水争いのあったこの2つの地域が水で仲良くなれるようにと名水百選では、それぞれ5つづつ選らぶという気遣いがあったという裏話も披露されました。「水に流そう~」って。(笑)厳しい中にもちゃめっけたっぷりな後藤さんの笑顔に緊張はすっかりとけてしまいました。
続いて2番目のテーマである「湧き水のメカニズム」

金武町と荻道大城の航空写真や断面図などを比べての説明はとてもわかりやすく、沖縄の湧き水の特徴とも言える琉球石灰岩台層の大きさが水量であるということが納得できました。
そして地下水の保全をするためには、できるだけ水を地下に浸透させることが大事であること。
そのためには普段から緑、土、命を意識することが大切だということがわかりました。
アスファルトの舗装などで雨水が側溝を通して流れ出ることで起こる危険な都市型洪水を防止するためにもとても重要なことで、地下水のメカニズムを知ることは、自然を守ること、命を守ることにつながります。
「水は40日で一回転」
「すでる(沖縄の方言では『すでぃる』)と言葉もあるように命は常に生まれ変わるもの。水は天からのもらい水であり、天に返さなければいけないものである」
常に神聖な気持ちで水に向き合いたいと思いました。それには謙虚な姿勢が大事なのだと感じます。

「名水百選の森の創出」
この曼荼羅図には、荻道大城の遺産や町並み、文化、そして湧き水が描かれており、その中心には森があります。
「森へつづくまちづくり」
地域の方々は名水によってこのようなすばらしい実践をされていることにとても感動を覚えました。
講演の内容をすべて記すことはできませんが、最後に後藤さんは私たちにこう問いかけました。
「カー(湧き水)は人間のためにあるのですか?」
地震、津波、台風、湧水、温泉
これはすべて自然現象です。
敵視してはいけない。
人間もその自然の中の一部にすぎない。
自然に会わせて生き物と同様に自然と共に暮らすという気持ちが大事なのではないか。
湧き水を自然共生のシンボルとして残すという視点を是非持っていてほしい。
そして、水に命を吹き込むという活動も必要。
科学的な物の見方も重要だが、やはり文化的な見方も大事。
それには『感性』が必要。
後藤さんの哲学ともいえる内容の濃いお話しを租借し、受け止め活動に結びつけていきたいと思います。
お忙しい中、本当によいお話をありがとうございました。

受講生の質問に答えながら中柱の説明をする後藤さん。